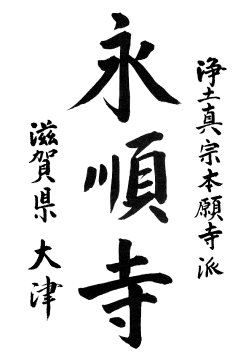[歴史]親鸞聖人の生涯(前史⑥)
今回は、前史⑤と少し重なるところもありますが、最澄がめざした天台の教えについて触れることにします。ただし、私自身は天台の教えについて門外漢のため不十分な内容になると思います。そのこと前もってお断りしておきます。
◆「教観二門」 天台宗では教えと実践の両方を大切にします。これを「教観二門」といいます。「教」は『法華経』に基づく教え、「観」は「止観」と呼ばれる瞑想行です。「教」からみてみましょう。
◆「一乗思想」
まず「一乗思想」です。「乗」というのは、悟りへ向かう教えを乗り物に譬えた語です。平たく言うと、人の能力や性質によって悟りに向かう道が異なるわけではなく一つであり、悟りは誰でも同じという思想です。
「一乗」に対して「三乗」という考え方があります。詳細は省きますが、要するに、悟りに至る道筋も行き着く悟りの世界も、その人の能力や性質によって異なるという見方です。最澄は、当時三乗思想を主張する法相宗(興福寺、薬師寺)と度々論争しました。
さて三乗と一乗とどちらが受け容れやすいかといえば三乗ではないでしょうか。能力や努力の度合いに応じて悟りの境地が違う方が私たちの常識に見合っていて納得しやすいですね。でも、それは、一部の人を除外する思想でもあるわけです。最澄は、それは大乗仏教の精神に反すると考えたのだと思います。
◆大乗「利他」の精神
そのことを示す最澄の『願文』という文をご紹介しましょう。これは、比叡山で修行と学問に専念していた頃に書かれたもので、僧としての生き方を情熱を込めて書かれた名文です。まず、
愚が中の極愚、狂が中の極狂、塵禿の有情、底下の最澄
《口語訳》
愚の中でも最も愚かで、狂った中でも最も狂った、髪はそっているが俗の塵にま みれた人間(有情)である最低の最澄。
と「愚者の自覚」に立った上で、五つの誓願を述べ、次のように締めくくっています。口語訳で紹介します。
ほとけに伏して願うところは、苦しみの世界から脱した喜びに一人浸ることなく、 安らぎに至る方法を一人だけ知ることなく、この世界のあらゆる生き物が等しく 苦しみの世界から脱し、安らぎに至れる方法を教えたい。
これが二十歳の最澄の思いでした。自らの悟りにだけ止まらずあらゆるものが等しく悟りに到れることを願い誓う利他の精神が見て取れます。まさに大乗精神の実現であり、「一乗」はその思想上の必然だったのです。
◆「一切衆生悉有仏性」
最澄の一乗思想は、釈尊の晩年から入滅までを説く『涅槃経』の「一切衆生悉有仏性」という思想とも深くつながっています。これは、一切の衆生が平等に悟りに到れるとするものです。誰もが仏になれる可能性、これを「仏性」といいますが、それが内在していると考えます。天台宗で一切の衆生という場合、人間はもとより動植物、国土も含めます。無機物にも仏性があるというのは、なかなか合点がいきにくいですが、動植物も死ねば最後は無機物に分解されますから、言えなくもないかと。
◆「十界互具」
「十界互具」も天台を代表する思想です。輪廻する世界を十に分けたのが「十界」で、仏界、菩薩界、縁覚界、声聞界、天上界、人間界、阿修羅界、畜生界、餓鬼界、地獄界です。これらを別々の世界とみるのではなく、たとえば、人間界にも地獄から仏が具わり、仏にも十界のすべてが具わっていると考えます。十界それぞれが互いにすべてを含んでいるので「互具」といいます。先に述べた「一切衆生悉有仏性」をもじって言えば「一切衆生悉有地獄」「一切衆生悉有餓鬼」・・・となります。そして、どの世界であっても「仏性」があると説かれます。
◆「止観」
次に実践である「止観」についてみておきましょう。理論である「教」は「止観」によってこそ完成するとされます。とはいえ、実践は実践でしか伝えられない上、私も門外漢ですから、基本的なことを私の知る限りでお伝えさせて頂きます。
「止」も「観」も、釈尊の時代から実践されてきた代表的な実践行であり、わかりやすく言えば瞑想です。まず、「止」というのは、心が静まって妄念や悩みが生じないようするための瞑想といえます。具体的な方法は、静かに座って鼻頭に意識を集中(止)して、出る息と入る息にだけ注意を向けます。他に意識が移ったら鼻頭に戻し、鼻中を通る空気(息)に注意を向けます。このように一点に集中することで心が静まり妄念や悩みが生じにくくなります。
これに対して「観」は、意識を一点に集中するのではなく、自由に動かします。たとえば、足が痛くなればそこへ、苛々してきたらそこへ意識を移して、「痛いな」「苛々しているな」と意識化します。こうすることで、妄念や悩みが起こりにくくなるのです。この「止観」を窮めていくことが、悟りにつながるとするのです。
◆「常行三昧」
天台宗の「止観」は、これらを元に「四種三昧」を行います。「三昧」というのは、サンスクリット語の「サマディー」の音写語で、訳すと「こころを静めて集中すること(定)」です。それには四種類あります。その一つ「常行三昧」を紹介しておきましょう。
阿弥陀仏を本尊とする堂内でひたすら口に念仏を唱え、心に阿弥陀仏のすがたを思い浮かべます。行として行う時は、九十日間、便所と入浴以外は食事も寝るのも立ったままという非常に厳しいものです。
「千日回峰行」という修行がありますが、これは「歩行禅」とも言われ、これも「止観」なのです。比叡山を伝教大師のお体、森を衣と見なして、それに沿って歩くことに精神を集中するのです。苦行と思われがちですがそうではないのです。
◆「諸法実相」
教観二門によって、最澄が目指した悟りとは、あらゆる存在(諸法)への先入観を取り除き、ありのままのすがた(実相)を、言葉によらずに感得することでした。これを諸法実相とよび、究極の境地、仏の悟りの世界とされました。
以上のような天台の教えを広めたいという最澄の願いは、叶ったのでしょうか。
◆天台法華宗の開創
それを実現するためには、『法華経』を中心とした「教観二門」を身につけた僧侶を育成しなければなりません。最澄は、唐から帰国した翌年、朝廷に願い出て、延暦25年(806)門弟から出家得度者(年分度者)を二名出すことを認められました。これは天台宗が一宗として正式に認められたということでもありました。ここに、天台宗(「天台法華宗」が正式名称)が開創したのでした。
ただ、二名の内一名は天台、もう一名は密教を修する者とされました。桓武天皇が密教に非常に大きな期待を寄せていたことがこのことからもわかります。最澄42歳でした。
◆大乗戒壇の設置
最澄が朝廷に求め続けたもう一つは、比叡山で独自に戒壇を設置することでした。戒壇は、正式の僧侶になるための戒律を授ける場所のことです。
当時は、比叡山で修行を積んでも、東大寺の戒壇院で受戒しなければ僧侶になれませんでした。しかも、その戒律は、部派仏教(小乗仏教)で行われていたもので、出家者のための戒律でした。最澄は、大乗仏教独自の新たな戒律「大乗戒」の承認を朝廷に求めたのでした。
この申し出が認められたのは、最澄の死後一週間後のことでしたが、このことによって、延暦寺は独自に僧侶を育成することが可能となりました。
延暦寺では『法華経』を中心とした天台のみならず密教、禅、念仏も並び修されましたので、いわば仏教の総合大学でもありました。このことが、後に鎌倉仏教の諸師が生まれる素地となったのでした。
弘仁14年(823)には、「延暦寺」の勅額を授かり、徐々に仏教教学の権威となり、「南都」に対して「北嶺」と呼ばれるようになっていきました。
また、平安京に近いことから平安貴族の信仰を集め荘園が寄進されました。貴族の子が「出家」すると、その出自によって山内での地位が決まるようにもなっていきました。
◆比叡山の世俗化
このようにして比叡山は、日本の大乗仏教の中心地としてその立ち位置を確立したのでした。しかしながら、天皇や貴族の尊崇を受ければ受けるほど政治に近接していったため、次第に世俗的な権力闘争の渦に巻き込まれていったのでした。武器を携えた僧兵が山内に生まれ、朝廷への要求が通らないと神木や神輿を担いで都になだれ込むようにさえなりました。
それに手を焼いた白河法皇は、
賀茂河の水、双六の賽、山法師、
是ぞわが心にかなわぬもの
といわれたそうです。
こうして比叡山は最澄の理想から離れて次第に世俗化していったのでした。
しかし、比叡山の僧侶すべてがそうだったわけではありません。世俗化をよしとせず、修行と学問に励んだ僧もいました。たとえば、日本の浄土教の祖といわれる源信は冥利を捨てて、横川に隠棲し『往生要集』を執筆したのでした。これが後に法然や親鸞が出現する背景となることも忘れてはならないでしょう。